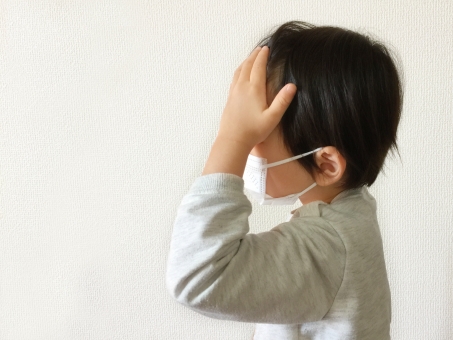子どもが思春期に入ると、親に何かと反発し、批判的な言葉を口にするようになります。ところで「思春期」って何?「思秋期」は何?「思春期」の子と「思秋期」の親が感情的にぶつかりあってしまうのは、よくあることですが、思春期の子と思秋期の親は、お互いに中途半端な自分にモヤモヤしやすい時期なので
■「思秋期」って何?
思春期の子を育てる親の年齢の多くが40代。「人生の秋」を思う時期という意味で「思秋期」と呼ばれています。
失った若さにちょっぴり未練を覚えながらも、老いを感じ始める思秋期の大人たち。
そんな自分に、モヤモヤ感を抱えやすい年代なのです。
思春期の子と思秋期の親は、お互いに中途半端な自分にモヤモヤしやすい時期だからこそ、感情的にぶつかりあってしまうのです。
「生意気言うな!」
「誰のおかげでメシが食えると思ってるんだ!!」
といった感情的な言葉をかけてしまい、険悪ムードになることがしばしば……。
「思春期の生意気さも成長の一プロセス」と頭ではわかっているのに、どうして感情を抑えられなくなってしまうのでしょうか?
■ 思秋期の親が思春期の子に感じる苛立ちの背景には、
この時期特有の「体調の変化」がありす。
がむしゃらに頑張れた30代と違い、少し頑張りすぎると直ぐに疲れを感じ、けだるさを覚えるのが思秋期の大人たち。
酒は以前より量は飲めないし、翌朝の目覚めも悪くなり、本人はまだまだ若いつもりでも、確実に体の衰えを感じてます。
そのギャップと、わが身のふがいなさにため息をつく一方で、同じことを難なくこなせる若さのジェラシーをふと感じてしまいます。
もう一つは、
■ 思春期と思秋期のまったく噛み合わない「世代間ギャップ」です。
「窮屈なしがらみを抜け出し、自由に向けて突っ走るだけ」――こうしたまっさらな夢を抱けるのも思春期という若さゆえですが、そんな子どもを心配そうに見つめながら、堅実に家庭を守り、着実に人生を生きて行こうとするのが、分別のある思秋期の親たちです。
ところが、思春期の子にとって、そんな親が言う説教など、「古くさい戯れ言」にしか聞こえないものです。
こうして親の教えや生き方を批判し、青臭い理想論を語る思春期の子の言葉に、思秋期の大人は苛立ちが募る・・・・。そして、「おまえに何ができる」「理想だけじゃ食っていけないぞ」などと、嫌味まじりの一言を加えてしまうのです。
■ 思春期の子たちは、
若い翼を思い切り広げながら、勢いよく上り坂を駆け上がっています。
一方、思秋期の大人は、後半生に向かって人生を見つめ直しながら、ゆっくりと下り坂を歩み始めているのです。
つまり、思春期の子と思秋期の親の「心のベクトル」は正反対なのです。
この理解のずれと噛み合わなさから、お互いに感情的になりやすくなるのです。
■ 子どもが思春期を迎えた時から、親の役割は変化します。
思春期の子どもが自分の人生課題に向き合い始めたように、思秋期の親にも向き合うべき人生課題があります。
子離れと共に重要度が増す「夫婦関係」の再構築、年老いていく親との関係、後半生向けてのライフプランや資金計画など、取り組むべき問題は山ほどです。子離れによって手に入れた時間こそ、こうしたテーマへの取り組みに適した時間です。
もちろん、子離れをしたと言っても、親の役割が必要なくなる訳ではありません。
一方、思春期では、対等な友だち関係の中、あるいは部活の先輩やコーチ、学校や塾の先生など、親以外の年長者との関わりの中で「自分らしい自分」を見つけようとします。
その途中で、多少の「やけど」を負うこともあるかもしれませんが、子どもには自力で軌道を修正する力があることを信じて、親は見守っていくのです。
未成年を保護する親としての養育責任は続きますし、「やけど」では済まされない危険を感じたときには、すぐに手を差し伸べる必要もあります。
とはいえ、思春期の子が「青春」に向けて歩き始めたときは、思秋期の親も「人生の秋」への歩みを進めていくタイミングです。
別々のベクトルに向かうお互いを尊重しながら、一つ屋根の下で共に生きていく、こうしたゆるやかな親子関係の再構築ができるのも、信頼関係でつながった親子だからこそではないかと思います。
思秋期の親にとって、思春期はとうり過ぎた道、逆に思春期の子供にとって、思秋期は行く道なのです。
■ 中学生の思春期、反抗期はいつまで続く?親がとるべき対処法は?
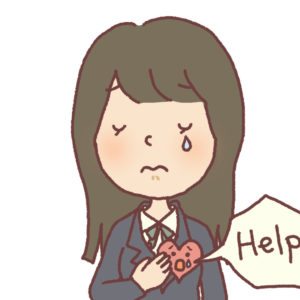
反抗期とは、子供が親に反抗的な態度を取る期間のことを言います。「イヤイヤ期」と呼ばれる、小さな子供の反抗期と違い、中学生の反抗期は、思春期特有のものです。子供は思春期に入ると、心身とともに大きな変化が訪れます。そうした子供の変化に関わらず、
■思春期の反抗期とは
第二次性徴期と呼ばれるこの時期は、男女とも、子供から大人へと成長する時期で、身体的には大人らしい体つきになるなどの大きな変化が見られるのです。
身体的に大きく成長すると、自分自身の急激な変化に気持ちがついていかないという子供も、中にはいます。
情緒的に不安定になるのもこの頃で、ちょっとしたことに一喜一憂するようになるのです。
そうした子供の変化に関わらず、親がこれまでと同じように接すると、子供との間に軋轢を生み出すことがあります。
■思春期の対応
たとえば子供は大人として扱ってほしいのに、親は子供扱いしたままだと、子供は欲求不満を覚えてしまうのです。
自我が出て自己主張が強い子供に対し、親の価値観を押し付けると、子供は反発するようになります。
思春期の子供が親に反抗する理由はケースバイケースですが、親と子供との間で考え方や価値観のズレが根底にある、という場合が多くあります。
■反抗期はいつまで続く?
思春期の反抗期がいつまで続くかというのには、個人差があります。
思春期の子供すべてが反抗期になるわけではなく、反抗期が始まる年齢も異なるのです。
一般的には、女の子は10歳頃から始まり、男の子は11歳頃から始まると言われています。
思春期の反抗期は18歳くらいまでですので、反抗期が数年間続くこともあります。
ただし、これはあくまでも目安ですので、参考程度にとどめておくのが良いでしょう。
■子供の反抗期対処法は?
思春期の反抗期は、男の子と女の子で異なります。
女の子は感情の起伏が激しくなり、相手によって態度を変える傾向があります。
それは両親に対しても同じで、子供から用事がある場合は話しかけてきますが、親から話しかけると、鬱陶しい、ウザいとばかりの態度をとります。
でもこれは、本人でもどうしようもないことで、親としては、暖かく見守ってやることが大事なのでは?
人間関係では、特に友達との付き合いに気を遣うようになり、友人関係の悩みが大部分を占める、という場合も少なくありません。
生理が始まり、身体のラインの変化に戸惑い、人知れず悩みを抱える場合もあります。
反抗期の男の子は、言葉遣いが悪くなることや乱暴になるなど、態度の変化が顕著です。
性的なことに興味を持ち、異性を意識する男の子も増えてきます。
素行が悪くなると、親に暴言を吐いたり、物を破壊したりする場合もあるのです。
男の子も女の子も、反抗期には挨拶をしなくなる、表情が乏しくなるなどの変化が見られます。
■まとめ
無理に直させようと叱らずに、様子を見るようにしましょう。
反抗期の子供は、自分の意見や考えを否定することを嫌がります。
子供の意見を否定ばかりしていると、子供は親に口を開かなくなってしまうことも考えられますので、どんな意見も否定せずに、一旦受け入れる余裕が、親には求められるのです。
帰りが遅い、夜遅くまで起きているなど、子供は親としてはつい叱りたくなる行動をする傾向がありますが、頭ごなしに叱らずに、「今日は遅かったけど、どこ行っていたの?」など、やんわりとした言い方をして、理由を聞くようにしましょう。
子供が何を考えて、どうしたいのかを理解しようと接することが、反抗期を乗り切るための、賢い親の姿勢と言えるでしょう。